はじめに
前回の記事では、ネットワークマーケティングの起源から特徴や利点についてご説明しました。
本稿では、とかく誤解を受けやすいこのビジネスモデルについて、とりあげます。
前回も述べたとおり、とくに「マルチ商法」といった言葉を使われる場合、悪いイメージしかわいてきませんか。
ネットワークマーケティングに携わっていて、「それって、ねずみ講じゃないの?」といった誤解や、「マルチってやつ?」といった偏見にさらされることはよくあることです。
まずはその誤解から解いていきたいと思います。
前回の記事は以下のリンクよりご覧いただけます。

ネットワークマーケティングはねずみ講か

もちろんNOです。
ねずみ講とは、正確には「無限連鎖講」と言います。
日本の法律では「無限連鎖講の防止に関する法律」(無限連鎖防止法)において規制され、これに関与する行為を禁止しています。
つまり、そもそもそういった組織は法律違反であり、存在しえないのです。
ではなぜ、ネットワークマーケティングがねずみ講と混同されるかというと、理由はその類似性にあります。
ねずみ講(無限連鎖講)は、商品が介在せず、お金だけがやりとりされる金銭配当組織を指します。
入会すると、まず主催会社に入会金を支払いますが、このお金が上位会員への分配として使われます。
つまり、自分と同様に、お金を主催会社に支払ってくれる人を下位会員として組織に加入させて初めて、自分が支払った出資金を回収したり、あるいはそれ以上の利益が得ることができる、ということになります。
無限連鎖講は、各参加者が新しい参加者を募集することによって成長します。
しかし、この成長は指数関数的であり、理論的にはいずれ参加者の数が人口を超える点に達します。
たとえば、1人が2人を募集し、その2人がさらに2人ずつ募集すると、参加者の数は急速に増加します(1, 2, 4, 8, 16, 32, …)。
このようにして、数ラウンド後には新しい参加者を見つけることが非常に困難になり、システムは破綻します。
無限連鎖講は、その性質上組織がピラミッド構造になります。
別名ピラミッドスキームとも言いますが、この組織構造と収益構造が、ネットワークマーケティングと似ていることから、誤解を受けるのです。
しかし、最初に明確に述べたとおり、ネットワークマーケティングは無限連鎖講とは異なります。その理由は次の通りです。

- 収益源
無限連鎖講では、ほとんどの場合新しい参加者からの入会金が主な源泉です。対してネットワークマーケティングでは、製品やサービスの販売が収益の主な源泉です。 - 適法性/違法性
無限連鎖講は、先に述べたとおり「無限連鎖防止法」において禁止されています。これは他の多くの国でも同様で、違法とされています。対してネットワークマーケティングは、法律と規制を遵守する限り、日本も含めて多くの国で合法とされています。 - 製品/サービスの存在
無限連鎖講では、実際の製品やサービスが提供されないか、あるいはされていても非常に価値が低かったり品質が悪かったりします。対してネットワークマーケティングは、実際の製品やサービスが提供され、ビジネスモデルはこれらの販売に基づいています。 - 報酬構造
無限連鎖講では、新しい参加者を募集することによってのみ報酬を得ることができます。対してネットワークマーケティングでは、会員を増やしただけでは利益は得られません。そこに商品の流通がおきて始めて収入になります。あくまで、起こした流通の規模に応じて収入が分配される実業であり、単に人を増やせばもうかる、といった虚業ではありません。 - 持続可能性
無限連鎖講のような指数関数的な成長は持続不可能であり、最終的には破綻します。対してネットワークマーケティングは、製品やサービスの実際の販売に基づくビジネスモデルであり、持続可能性が高くあります。
このように、ネットワークマーケティングとねずみ講(無限連鎖講)は明確に異なるものです。
ただし、ネットワークマーケティングも法規制を受けます。日本においては、特定商取引法の中で「連鎖販売取引」として定義されています。
あなたがもしネットワークマーケティングに取り組もうとするなら、この法律を遵守しなくてはなりません。違反すると、次項のような誤解の元になります。
マルチ商法は悪か

意外に思われるかもしれませんが、こちらもNOです。
正確には、正しいマルチ商法と悪いマルチ商法(悪徳マルチ)がある、ということになります。
これまで述べてきたとおり、ネットワークマーケティングの同義語であるマルチレベルマーケティングを言い換えたものが「マルチ商法」であり、本来はそれ自体が違法性のあるものを指す言葉ではありません。
さまざまな報道などにより、マルチ商法=悪のイメージがついてしまいましたが、法律や規制にしたがっていれば違法ではありません。
ではなぜ、悪徳マルチがはびこり、悪いイメージがついてしまったのでしょうか。まずは法律のほうからおさえていきましょう。
ネットワークマーケティングの法律的な位置づけ
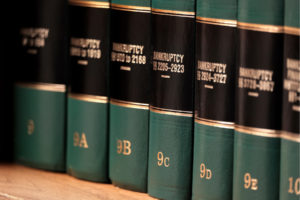
ネットワークマーケティング(マルチレベルマーケティング、マルチ商法)は「連鎖販売取引」として特定商取引法に定義されている、ということは先に述べました。
具体的には、第33条で次のように規定されています。
- 物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
- 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
- 特定利益が得られると誘引し
- 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの、であるといった感じです。
堅苦しい言葉が並ぶとなんとなく悪いイメージがわいてきてしまいますが、法律独特の言い回しのため、このような文章はどうしてもネガティブな印象を受けてしまいます。
逆に言えば、法律に規定されているということは、つまり法律で認められているビジネスモデルである、ということもイコールだと言えます。
ただネットワークマーケティングは、一歩間違えば無限連鎖講の仕組みに近づいてしまう可能性があるため、法律でも義務や禁止事項が明確に記載されています。
ネットワークマーケティングに取り組む場合はこれらに注意しなくてはなりませんし、もしあなたが誘われる立場である場合は、この義務や禁止事項がしっかりと守られているかどうかを確認することで、「正しい」商法であるかどうかが判断できる、ということでもあります。
主なものについて、かいつまんでご説明したいと思います。より詳細について正確にお知りになりたい方は、消費者庁のホームページなどでご確認ください。
- 氏名等の明示
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)は、連鎖販売取引をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して、(1)その氏名、(2)特定負担をともなう(会費や商品の購入)取引についての契約を勧誘する目的である旨、(3)その勧誘に係る商品または役務の種類を、告げなければなりません。
こういったことを隠してビジネスをおこなうことはできない、ということです。当たり前のことなのですが、特に(2)を告げないと、信頼関係が一気に崩れてしまいますし、そもそも違法です。
- 禁止行為
次のような行為は禁止されています。
(1) 契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
(2) 契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
(3) 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
うそや隠しごと、威迫(人をおどしたり不安を感じさせたりして、従わせようとすること)をしてはいけないのは、ネットワークビジネスに限らず、他の商取引でも同じです。
- 広告の表示
広告をする場合には、統括者や勧誘者の氏名、商品の種類、特定負担や特定利益の計算方法など、表示内容が細かく義務づけられています。
- 誇大広告等の禁止
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
この点も、どの商取引でも同じです。ネットワークビジネスについては、つい大きく(あるいは良く)みせようとしてしまいがちですので、注意が必要です。
上記以外にも、未承諾者に対する電子メール広告の提供禁止や、書面の交付等も規定があります。ネットワークビジネスに取り組むに当たっては、しっかりと下調べをし、違反しないよう(または違反に巻き込まれないよう)注意しましょう。
まとめ
ここまで、ネットワークビジネスが関係する商取引について、違法なものとそうではないもの、どのようなときに違法になるか、見極めかたなどについて、法律の記載内容を参照しながら重点的に解説してきました。
誤解を受けやすいという側面には、これまでの歴史や、市場が生み出した悪い側面の影響があったことは否めません。
だからこそ、ネットワークビジネスに取り組むときには、真摯さと知識が必要になります。
誤解を生みやすいという一側面がある事実には、なんらかの原因がひそんでいる可能性があるということです。
そういったことを払拭し相手に理解してもらうためには、まず自らが納得しなくては始まりません。しっかりと意識していきましょう。

こんにちは、ホームページに訪れていただき、ありがとうございます。
京都市在住の3児のパパです。
私の人生は、ドテラのエッセンシャルオイルとミネラルの驚くべき効果に出会うことで一変しました。
これらの自然の恵みは、私たちの身近な健康の悩みを解消するだけでなく、収入の悩みにも対応する権利収入型のビジネスの仕組みを構築する手助けをしてくれるのです。
ドテラの商品の質の高さと、そのネットワークビジネスの仕組みに心から共感し、私はチームとしての活動をスタートさせました。
私たちのチームは、同じ価値観を共有する仲間と共に、より健康で豊かな生活を手に入れることを目指しています。
このホームページでは、ドテラのエッセンシャルオイルやミネラルについての情報、そしてそのビジネスチャンスに関する情報を共有しています。
そして、私たちはブログやSNS等のオンラインを活用して、仕組みが自動的に集客してくれるシステムの構築にも取り組んでいます。
ただし、全てオンラインだけで完結するわけではありません。
Zoomや実際に会っての活動も重要な要素となります。
しかし、その点でもチームとしてのしっかりとしたサポートがありますので、オンライン活動に不慣れな方や、直接会うことに不安を感じる方でも、安心してビジネスを始めることができます。
私たちの活動に共感し、一緒に成長していけるビジネスパートナーを心から募集しています。
健康や収入に関する夢や悩みを持っている方、私たちと共に新しい一歩を踏み出しませんか?

 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑ ↑ ↑

コメント